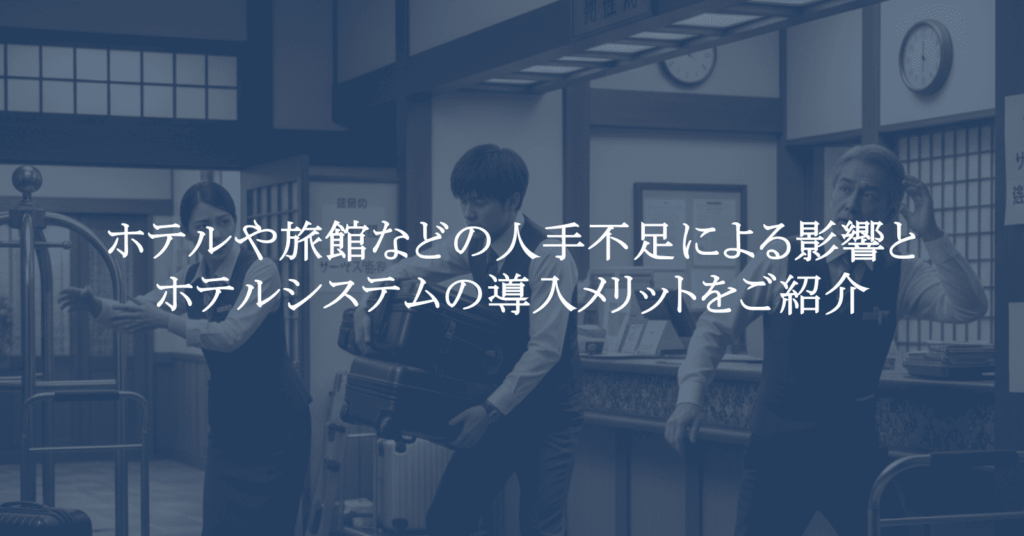
本記事では、全国3,500施設以上のホテル・旅館への導入実績を持つ当社が、宿泊管理システム(PMS)や自動チェックイン機などの提供を通じて得た現場の知見と最新の業界トレンドを基に、宿泊施設の人手不足を解消するためのIT・DX活用の効果とメリットを解説します。実際の導入事例から見える成果や、経営効率化・人材最適化につながる実践的なポイントを紹介し、宿泊業の持続的成長を支援するためのヒントをお届けします。
旅館・ホテルの【おもてなし】が危機に直面している!?
地方を中心に旅館やホテルは、「おもてなし」を核とする経営スタイルが、現在、構造的な変化により揺らいでいます。
例えば、国内宿泊・飲食サービス産業では2030年までに約50万以上の労働力ギャップが生じる可能性が指摘されており、World Travel & Tourism Council(WTTC)の報告では、2035年には日本の観光・宿泊部門が世界でも最大の労働力不足(約29%)に直面するとされています。
参照元:https://www.japantimes.co.jp/business/2025/10/10/toursim-labor-shortage/
加えて、物価・食材・光熱費などの上昇が宿泊施設のコスト構造に直接的な圧力をかけており、夕食付きプランや部屋食など従来のサービスを維持することが難しくなっています。こうした複数の要因が重なり、地域に根ざした宿泊業が“おもてなし”を提供し続けるための経営基盤そのものを問われているのです。
目次
慢性的な人手不足と物価高騰が直撃
宿泊業を取り巻く環境では、深刻な人手不足と物価高騰という二重構造の圧力が明らかになっています。Teikoku Data Bankの調査によると、宿泊・旅館業界では労働力の確保が特に難しい状況で、「客室担当1人あたり担当数の増加」「従業員賃金の低迷」などが顕在化しています。
また、世界的なエネルギー・食材価格の高騰を背景に、宿泊施設の「宿泊料(CPIベース)」が2023年4~7月期で前年同期比11.2%増という報告もあり、コスト上昇の実感が数字としても出ています。
このように、スタッフ確保の難しさとコスト面の負荷が同時に宿泊施設経営を圧迫しており、結果的に「おもてなし」を提供するための余裕が縮まっているのです。
参照元:https://www.tokyofoundation.org/research/detail.php?id=965
外資系ホテルの進出による人材流出
近年、国内宿泊マーケットには外資系ホテルチェーンの進出が加速しており、高単価なポジションや国際ブランドの求人が地方宿泊業界の人材を引きつけています。結果として、地域に根差した旅館・ホテルから優秀な人材が流出する傾向が見られ、地元の宿泊施設では採用競争力の低下に直面しています。
例えば、多くの宿泊事業者が「働きがい」「報酬」「キャリアパス」という観点で負荷を感じており、若手への魅力訴求が難しくなっています。
このような人材移動の背景には、都市部や高級宿泊施設を中心とする外資系ブランドの給与・福利厚生の充実があります。宿泊施設にとっては、単なる「人を確保する」だけでなく、「人を引き止める環境づくり」が今まさに経営の分岐点となっています。
食事提供の縮小や素泊まりプランの増加による収益圧迫
地方旅館・ホテルで食事付きプランや部屋食といった従来の“おもてなしメニュー”を維持することが困難になり、「素泊まり」や「泊食分離(別途食事提供)」プランの採用が増えています。
これは、調理・配膳・人材・食材コストの上昇が背景にあるためです。宿泊料金以外の収益源を確保できない状態は、客単価の低下を招き、経営構造を直撃します。加えて、宿泊施設のコスト増加が収益性に影を落としており、投資家・運営者ともに「持続可能なサービス提供モデル」の再検討を迫られています。
この変化が意味するのは、単なるサービスの変更ではなく、業態・提供価値そのものの再定義であり、「おもてなし」の価値をどう維持しながら収益を確保するかが中核課題となっています。
参照元:https://www.hotelmanagement-network.com/news/investors-cautious-as-japan-hotel-costs-climb/?cf-view
従来の経営モデルが限界に近づく
地方に根差した旅館・ホテルの多くが、従来型の「料理・部屋・接客」で客室稼働を上げ、宿泊料+食事料金で利益を確保するモデルを採用してきました。しかし、上述の人手不足・コスト高・プランシフトの三重打撃により、このモデルの持続可能性が問われています。
特に、食事付き宿泊プランが縮小する中で、客単価が落ちる一方、固定費(建物・人件・光熱等)は変わらず掛かり続けるため、経営継続性に黄色信号が灯っています。専門調査でも、宿泊業における労働供給の限界が供給側制約として明記されており、根本的な経営転換を余儀なくされています。
「泊食分離」の流れが止まらない理由
「泊食分離」とは、宿泊料金と食事を別料金とするプランを指し、近年宿泊施設で急速に広がっています。その主な理由は、食材費・人件費・調理設備維持の負担が増す中で、食事付きプランを継続するリスクが高まっているためです。
また、宿泊者のニーズ自体も変化しており、「夕食を外食で済ませる」「部屋食は不要」という選択をする若年層・観光客も増加しています。これにより、施設側としてはサービス内容をプランごとに柔軟に設計せざるを得ず、結果として「宿泊+食事一体型」モデルからのシフトが加速しています。
客単価の減少が続く地方旅館の現実
地方旅館・ホテルでは、食事付きプランの縮小・素泊まり採用の増加に伴い、客単価(宿泊料+付帯売上)の減少傾向が確認されています。固定費は変わらない中で客単価が下がることは、収益性を直撃します。
加えて、宿泊者の「コストパフォーマンス重視」の姿勢が強まっており、サービス過剰やオーバースペックな【おもてなし】を価格に反映しづらくなっています。このため、地方の宿泊施設は「低コスト・低付加価値」だけではなく、「付加価値ある体験」での差別化が益々求められています。
現場スタッフの疲弊とサービス品質への影響
経営環境が厳しくなる中、現場スタッフ—特に調理・接客部門—の業務負荷が増大し、疲弊が進んでいます。人員が不足すると、一人あたりの担当領域が広がり、結果的に「おもてなし」に向ける時間・余裕が奪われがちです。
サービス品質が低下すると、リピート率や口コミ評価にも影響を及ぼし、ブランド価値そのものの崩壊を招きかねません。宿泊業界の調査では、宿泊・飲食業界の求人倍率が他業種と比して三倍以上というデータもあり、高ストレス環境が背景にあるとされています。
ノンコア業務が経営を圧迫する実態
宿泊施設の【おもてなし】を支えるには、調理・接客・地域体験といったコア業務に人的リソースを集める必要がありますが、現状ではチェックイン対応、予約管理、請求処理、清掃スケジューリングなどの「ノンコア業務」が膨大かつ煩雑になっており、経営リソースを圧迫しています。
こうした管理業務の手間を削減できなければ、人材を“稼働効率の低い作業”に使ってしまい、本来注力すべきサービス提供が後手に回るリスクがあります。近年の宿泊業界では、こうした“管理の複雑化”が地方の宿泊施設の競争力を削ぐ要因のひとつとして指摘されています。
チェックイン対応、請求処理、予約管理の煩雑さ
宿泊施設では、
- 顧客データの取り扱い
- チェックイン/チェックアウト対応
- 宿泊プラン・部屋タイプ管理
- 請求書/領収書発行
- OTA(オンライン旅行代理店)や自社サイトからの予約調整
- キャンセル対応
など、日常運営における“管理業務”が多岐にわたります。
こうした業務が属人的・手作業で行われている施設では、人的ミス・時間ロス・コスト増が常態化し、結果としてサービス提供側の人材を圧迫します。これが、地方の宿泊施設が【おもてなし】に集中できない原因のひとつとなっています。
事務負担が“おもてなし”の時間を奪う
本来、宿泊施設において最も価値を生むのは「人が関わるサービス体験」、つまり調理・接客・地域体験への注力です。しかし現場では、事務処理や予約管理といった業務が人材を占有してしまい、接客スタッフや調理スタッフが「書類」「端末入力」「チェックリスト作成」などに追われてしまっています。
このような状況では、「旅館が一番輝きを発揮する対話・気配り・地域体験提供」の時間が奪われてしまい、“おもてなし”の質を維持・向上させるうえで大きな制約となります。
HOTEL SMARTでは、宿泊施設の課題を解決し、さらなる顧客満足度の向上と、収益の向上を実現する宿泊施設向けオールインワンシステムです。サービスの概要や導入事例、具体的な運用方法をまとめた資料をお配りしております。ご検討のお役に立てください!
自動化・効率化がもたらす人材再配置の可能性
宿泊施設が今後生き残るためには、ノンコア業務の自動化・効率化を通じて、人的リソースを「人にしかできない価値創出業務」へシフトさせることが鍵です。例えば、セルフチェックイン/チェックアウト、予約・料金管理システム、顧客データベースの活用によるパーソナライズ提案など、IT導入により事務作業を削減し、調理・接客・地域との連携など“核”となる業務に人材を再配置できます。こうした転換は、宿泊施設の収益構造とサービスモデルをアップデートする上で、現実的な「生き残り策」として注目されています。
IT導入で「人の価値を最大化」するホテル経営へ
IT/システムを導入することで、例えばチェックイン・チェックアウトや請求処理、在庫管理等のルーチン作業が自動化され、ミス・重複作業が削減されます。
その結果、スタッフは“人と人の接点”や“体験企画”など、機械では代替できない価値領域に集中可能です。宿泊業における“人材”の価値を最大化するには、「何を機械に任せ、何を人が担うか」を明確に設計することが成長の鍵となります。
厨房・接客・地域連携へのリソースシフト
自動化により生まれた余力を、厨房や接客だけでなく、地域体験・観光資源との連携へとシフトさせることで、宿泊施設の“差別化”や“付加価値”を高めることができます。
例えば、地元食材を用いたワークショップ、滞在中の地域散策ガイド連携、宿泊と地域体験の融合プランなどが挙げられます。これにより「ただ泊まる」だけでない体験を提供し、客単価アップ・リピート促進にも繋がります。
チェックイン・管理システムによる業務効率化の実例
近年、宿泊業界ではチェックイン・ホテルシステム(予約管理、顧客データ活用、セルフサービス端末など)導入が進みつつあります。こうしたシステムにより、少ないスタッフでもスムーズな運営が可能になり、事務処理コスト・人件コストの削減を実現できます。
更に、顧客データを蓄積・分析することで、再来訪を促すマーケティング(アップセル・クロスセル)にも活用でき、収益モデルの強化に直結します。実際、宿泊業市場の拡大予測の中で、デジタルソリューションの採用が重要トレンドと記されています。
スタッフ不足でもスムーズな運営を実現
例えばセルフチェックインシステムや現金精算機を利用すれば、フロントスタッフの人数を抑えつつ、チェックイン時の待ち時間短縮や人的ミス軽減が可能です。
これにより、接客スタッフが本来注力すべき【歓迎・案内・地域体験の提案】などのコア業務に時間を回せるようになります。
顧客データ活用で再来訪・アップセルの促進
予約管理システムにより、顧客の過去宿泊履歴・要望・支出傾向を保存・分析することで、滞在中または再来時に「この宿泊客には〇〇を提案」「この地域体験を組み込む」といったアップセル提案が可能になります。これが売上向上・客単価増加の施策として有効です。
参照元:https://dimensionmarketresearch.com/report/japan-hospitality-industry-market/
地域に根ざした宿泊業が生き残るために
地域の旅館・ホテルが今後も存在価値を保つためには、テクノロジーと【おもてなし】を対立させるのではなく、両者を共存・融合させる戦略が不可欠です。
人材・地域資源・宿泊サービスとシステム化された運営が連携すれば、「地域ならでは」の体験+効率化されたサービス提供という新しいビジネスモデルが描けます。
さらに、デジタルを単なる「コスト削減ツール」としてではなく、「価値創出のための手段」として位置づけることで、地方における宿泊業のイノベーションにも繋がり得ます。これからは、地域観光の活性化と宿泊施設の収益モデル改革が一体となる時代と言えるでしょう。
人とシステムの役割分担
宿泊施設運営において、IT・システムで代替可能な業務(チェックイン、データ処理、請求発行等)と、人が行うべき領域(接客、料理、地域体験提案等)を明確に分け、両者がシームレスに連動する体制づくりが鍵です。
この体制を整えることで、人材を【サービス創造】に振り向けられ、顧客満足度・リピート率・口コミ評価を高められます。
デジタルを“コスト削減”ではなく“価値創出”として活かす
システム導入は「人件費削減」のためだけではなく、「体験の質を高め、他にはない宿泊価値を提供する」ためのプラットフォームとして活用すべきです。
デジタルを活用して、「地域の魅力を発信する」「パーソナライズされた宿泊体験を提供する」など、宿泊単価と顧客満足を両立させる方向に転換することが、地方の宿泊施設の復権を促します。
地方から始まる宿泊業イノベーションの可能性
旅館・ホテルは「地域ならでは」の強み(自然、温泉、食文化、ローカル体験)を掛け合わせ、デジタル&効率運営を支えることで新たな価値を創出できます。
例えば、滞在前後のデジタル予約・セルフチェックイン・地域体験のアレンジをワンストップ化することで、宿泊+体験という“複合価値”を提供し、観光需要の変化に柔軟に応えることが可能です。
ホテル・旅館向けのトータルソリューションをご紹介

弊社が提供してるHOTEL SMART(ホテルスマート)のセルフチェックインは、部屋数の多いシティホテル (100室以上) や全国に展開されているチェーンホテルから、旅館やリゾートホテルでも、フロントを完全無人にして運用している実績があり、フロント業務の削減に寄与します。
加えて、プリチェックインを利用することにより宿泊日当日のフロントにおけるチェックイン作業は最短10秒で完了するため、顧客満足度の向上にも効果を発揮します。
NECが提供しているホテル基幹業務システム『NEHOPS』やOracle社が提供しているホテル管理システム『OPERA』など他社サービスのホテル管理システムと連携実績があり、既存のオペレーションを変えずに導入することができます。
また、ホテルシステムをまだ導入されていない運営中の宿泊施設やこれから開業を予定されている施設様にはチェックインシステムと一体型となったホテル管理システム(PMS)も併せてご利用いただけます。
弊社のホテル管理システム(PMS)では予約管理、客室管理などはもちろん、清掃管理や食事管理なども標準で搭載しており、追加費用が発生せずにノンコア業務を自動化・効率化いただけます。制度改正にもクラウド更新で柔軟に対応し、現場の負担軽減と業務品質の向上を同時に実現します。
まとめ
旅館・ホテルが直面している課題は多岐にわたりますが、「人手不足・物価高・人材流出」という三重の構造変化が【おもてなし】という宿泊業の核心に影を落としています。
その一方で、ノンコア業務の自動化・IT導入、そして人が輝く業務へのリソース再配置といった転換が、経営の新たな可能性を示しています。地域ならではの強みを生かしつつ、テクノロジーと融合した運営モデルを構築することで、宿泊業は再び価値を発揮できるでしょう。
