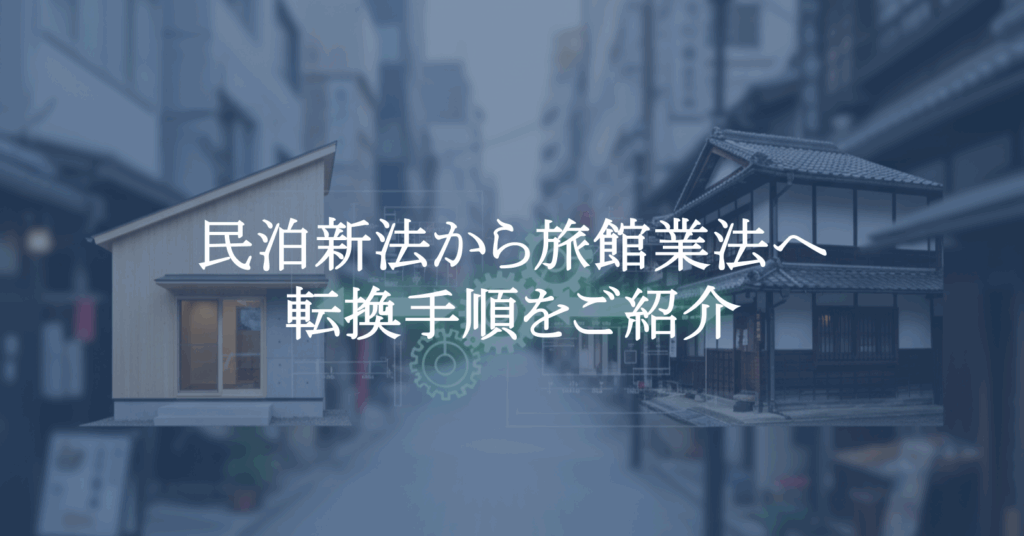
本記事では、民泊新法から旅館業法へ切り替えるために必要な要件、申請手続き、用途変更・消防対策・現地調査の流れを専門的に解説。旅館業法で求められる設備基準や運営義務、導入すべき管理システムまで、開業準備に役立つ実践情報を解説します。全国3,500施設以上の民泊からホテル・旅館に対し、宿泊管理システム(PMS)や自動チェックイン機を提供してきた実績から得られた現場の知見と、最新の業界トレンドをもとに、宿泊施設の経営に役立つ実践的な情報をお届けします。
目次
民泊新法と旅館業の違い
民泊新法(住宅宿泊事業法)は許可取得のハードルが低く柔軟な運用が可能な一方、旅館業法は常時宿泊を前提とするため設備・衛生・防火の基準が厳格です。転換では「用途変更の可否」「消防計画の再設計」「人員体制」などハード・ソフト両面を総点検する必要があります-。自治体ガイドの差も大きいので、事前相談で要件のブレを解消し、工程・費用・責任者を明確化して進行管理しましょう。なお、予約・料金・苦情対応の運用規程やリスク管理(事故時の連絡網、返金ルール)の整備も同時進行で行うと審査・運営の信頼性が高まります。
民泊新法とは?
民泊新法は、自宅や空き家を宿泊施設として活用できる制度で、営業日数は原則年間180日以内と定められています。開業にあたっては、近隣住民への説明や苦情対応体制の整備、衛生管理が必須です。ホテル・旅館のような大規模設備要件はなく、簡易な構造でも許可を受けられますが、清掃・リネン交換、感染症対策、宿泊者名簿や苦情記録の保存など、運営管理の徹底が求められます。
管理を専門業者に委託したり、IoTを活用した無人運営も可能ですが、地域条例による規制やマンション規約での制限があるため、事前に必ず確認しましょう。さらに、事故時の連絡体制や返金ルールなどリスク管理を整備しておくと、開業後のトラブルを防ぎ、安心して運営できます。
民泊新法と旅館業法の違い
民泊新法(住宅宿泊事業法)は、住宅を活用して宿泊サービスを提供できる仕組みで、営業日数は年間180日以内に制限されます。簡易な設備でも許可が得られ、運営管理を外部委託したり無人運営を導入することも可能ですが、衛生管理や苦情対応の体制整備が必須です。
一方、旅館業法に基づく旅館・ホテル・簡易宿所は「常時宿泊」を前提とし、床面積やトイレ数、防火設備、フロント設置など厳格な施設基準や人員配置が求められます。許可取得後も名簿管理や事故報告、立入検査対応が義務付けられ、より継続的で本格的な運営が必要となります。
HOTEL SMART(ホテルスマート)では、宿泊施設の課題を解決し、さらなる顧客満足度の向上と、収益の向上を実現する宿泊施設向けオールインワンシステムです。サービスの概要や導入事例、具体的な運用方法をまとめた資料をお配りしております。ご検討のお役に立てください!
必要な準備物
転換には多くの準備資料が必要です。具体的には、図面(平面・立面・設備)や避難経路図、面積・客室数の算定表、構造・内装仕様、給排水・換気・電気系統図など建築関係の資料に加え、消防設備計画や衛生管理計画書を整備します。さらに、従業員配置・教育計画、運営規程、苦情対応フロー、近隣説明記録、宿泊約款など運営面の文書、身分証や登記事項証明、賃貸物件の場合は使用承諾書も必要です。
また、信頼性を高めるために作成者資格・監査者・根拠法令・更新履歴を明記することが推奨されます。予約・料金・リスク管理(事故時の連絡網や返金ルール)も併せて整備することで、審査や運営がよりスムーズに進みます。
許可申請の手続き
旅館業法の許可取得に向けた申請手続きは、準備資料の収集とは別に進めるべき具体的な流れがあります。
まず、自治体の窓口で事前相談を行い、建築基準法や消防法上の適合性を確認します。その後、申請書に必要事項を記入し、添付書類一式とともに保健所へ提出します。提出後は、消防署・保健所による現地調査・立入検査が行われ、避難経路や消防設備、衛生管理や人員配置が基準通りかチェックされます。指摘があれば改善報告を提出し、最終確認を経て許可証が交付されます。
申請から交付までには数週間〜数か月かかることが多く、設計者や消防設備士と連携して早めに相談・調整を行うことが円滑な進行の鍵です。
旅館業法の種類別の必要な手続き
旅館業法の許可取得は、施設タイプごとに必要な手続きが異なります。
ホテル・旅館は常時宿泊を前提としており、フロント機能やロビー、共用部の整備、防火戸や避難経路など厳格な基準を満たす必要があります。
簡易宿所は相部屋やドミトリー利用を想定しており、床面積や客室数の算定が重要で、比較的柔軟な基準で運営が可能です。下宿営業は長期滞在者向けで、食事提供や共同利用設備の衛生管理が焦点となります。さらに、食事を提供する場合は食品衛生法に基づく飲食店営業許可や営業届も併せて取得が必要です。
申請の流れは、建築基準や消防の同意確認を経て、旅館業許可を取得し、その後に食品衛生関連の許可を並行または順次進めるのが一般的です。施設の種類に応じた基準を理解し、逆算的にスケジュールを組むことが円滑な開業のポイントです。
現地調査
旅館業許可では通常、保健所と消防の現地調査が実施され、客室・共用部の衛生、避難経路や消防設備の適合を確認します。流れは①事前相談②図面・衛生/消防計画提出③消防同意④保健所へ申請⑤現地調査⑥指摘是正⑦許可交付。準備は平面・設備図、避難経路図、衛生管理計画、消防設備の証明、名簿様式などを整えておくとスムーズです。
法令遵守と安定運営に必要なシステム
旅館業法に基づいて運営を始める事業者にとって、チェックインシステムやPMS(宿泊管理システム)の導入は単なる効率化ツールではなく、法令遵守と安定運営のための必須インフラとなります。例えば、旅館業法では宿泊者名簿の整備や保存、苦情対応の記録、清掃・衛生管理体制の証明が求められ、立入検査でも提示が必要です。これらを紙で管理すると漏れや紛失リスクが高まりますが、システム化すれば自動保存や検索が可能となり、監査対応がスムーズになります。
HOTEL SMART(ホテルスマート)がオールインワンで提供してるチェックインシステムやPMS(宿泊管理システム)では、チェックイン時の本人確認や外国人宿泊者のパスポート情報記録もシステム連携で正確に処理できます。旅館業法に沿った記録保持と業務効率化を同時に実現できる点は、新規開業者にとって特に大きな導入メリットです。
まとめ
民泊新法から旅館業法へ転換する際は、建築用途変更や消防計画の再設計、施設基準(床面積・採光・トイレ数・避難経路など)を満たす改修が必要です。審査や現地調査も厳格になるため、事前相談と準備が不可欠です。
一方で、旅館業許可を得ることで通年営業が可能となり、集客力や信頼性が大幅に向上します。ここで重要となるのがPMSやチェックインシステムの導入です。宿泊者名簿や清掃記録の電子管理、本人確認や外国人情報の正確な取得、料金・予約の一元化など、旅館業法で求められる運営義務を効率的に満たすことができます。
結果として、法令遵守と業務効率化を両立し、利用者からの信頼を高めながら安定した運営基盤を築けます。

